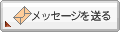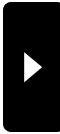2025年05月06日
LUXMAN 5M21 修理 鹿児島県より ATTENUTOR分解修正、各部点検
今回のご依頼は、LUXMAN 5M21 鹿児島県からです。


梱包の開封時に、嬉しい差し入れに気が付きました。

M様、いつもお世話になっております、差し入れのお心遣いにお礼申し上げます。

今回の依頼内容は、各部の点検とメンテナンスとのことです。

早速、電源の投入を確認し、音出し確認を進めて

本体の裏面のアッテネーターにガリノイズが生じます。

キャビネットと


底面のカバーを取り外し、

内部のクリーニングを進めます。

画像では、判りにくいですがスッキリしました。

先ず、基板の半田付けや


ワイヤー類を点検し、

アッテネーターの分解作業に移ります。

先ず、内側のプレートを取り外し、


VRを抜き取ります。

そして、接点クリーナーを吹きかけて、

VRを組み戻し、

内側のプレートを組み戻します。

各基板を点検し、

半田付けの怪しい部分を付け直します。


そして、電源回路等を点検し、


電源の投入を確認し、

キャビネットを組み戻し、

各操作を点検し、

流しテストで音出し確認し作業終了です。

梱包の開封時に、嬉しい差し入れに気が付きました。
M様、いつもお世話になっております、差し入れのお心遣いにお礼申し上げます。
今回の依頼内容は、各部の点検とメンテナンスとのことです。
早速、電源の投入を確認し、音出し確認を進めて
本体の裏面のアッテネーターにガリノイズが生じます。
キャビネットと
底面のカバーを取り外し、
内部のクリーニングを進めます。
画像では、判りにくいですがスッキリしました。
先ず、基板の半田付けや
ワイヤー類を点検し、
アッテネーターの分解作業に移ります。
先ず、内側のプレートを取り外し、
VRを抜き取ります。
そして、接点クリーナーを吹きかけて、
VRを組み戻し、
内側のプレートを組み戻します。
各基板を点検し、
半田付けの怪しい部分を付け直します。
そして、電源回路等を点検し、
電源の投入を確認し、
キャビネットを組み戻し、
各操作を点検し、
流しテストで音出し確認し作業終了です。
2025年05月05日
DIATONE DP-EC1MKⅡ 修理 埼玉県より アームベース分解修理、ベルト交換修理、他
今回のご依頼は、DIATONE DP-EC1MKⅡ 埼玉県からです。


故障内容は、フルオート機能の故障とのことです。

早速、電源の投入を確認し、

制御系の点検で回転数等は順調です。

続いて、オートスタートの操作を試みますが、動作できません。

尚、手動での操作で音出しは順調です。

ターンテーブルを抜き取り、


底蓋を取り外し、

内部のクリーニングを進めます。

元々ホコリ等は殆どありませんでした。

アームベースの点検を進めて、青印と赤印の部分で

ベルトが溶解付着しております。

センサープレート類を取り外し、


プーリー類を抜き取り、


クリーニングを進めます。


2種類のベルトを準備し

プーリーと組み戻し、

センサープレートを取り付けます。

続いて、アームのキューイングの駆動ベルトを抜き取り、

プーリー類をクリーニングし

右側の交換用のベルトを準備し

組み付けます。

そして、センサー類を点検し、

基板類の点検を進めて、


モーターのシャフトカバーを取り外し、


オーリングの点検を進めて、

本体を組み立てます。

電源の投入を確認し、

各操作を点検し、

流しテストで音出し確認し作業終了です。

故障内容は、フルオート機能の故障とのことです。
早速、電源の投入を確認し、
制御系の点検で回転数等は順調です。
続いて、オートスタートの操作を試みますが、動作できません。
尚、手動での操作で音出しは順調です。
ターンテーブルを抜き取り、
底蓋を取り外し、
内部のクリーニングを進めます。
元々ホコリ等は殆どありませんでした。
アームベースの点検を進めて、青印と赤印の部分で
ベルトが溶解付着しております。
センサープレート類を取り外し、
プーリー類を抜き取り、
クリーニングを進めます。
2種類のベルトを準備し
プーリーと組み戻し、
センサープレートを取り付けます。
続いて、アームのキューイングの駆動ベルトを抜き取り、
プーリー類をクリーニングし
右側の交換用のベルトを準備し
組み付けます。
そして、センサー類を点検し、
基板類の点検を進めて、
モーターのシャフトカバーを取り外し、
オーリングの点検を進めて、
本体を組み立てます。
電源の投入を確認し、
各操作を点検し、
流しテストで音出し確認し作業終了です。
2025年05月03日
TRIO KA-4700 修理 沖縄県内より I.C交換修理、コンデンサー交換修理、他
今回のご依頼は、TRIO KA-4700 沖縄県内からです。
故障内容は、フォノ入力やチューナー入力、AUX入力の不具合とのことです。

又、部品取り機もお預かりしております。

早速、電源の投入を確認し各操作の点検を進めてみますと、フォノ入力で激しいノイズが生じます。
又、チューナーとAUXの入力も不安定です。

キャビネットを分解し、

各部の点検を進めて、インプットセレクター回路の故障と判明いたしました。

基板の細部の点検で、I.Cの不具合が見つかりまして、

部品取り機から、赤印の交換用を抜き取りこちらを移植いたします。

そして、周辺の劣化したコンデンサーを取り替えて、

各基板の点検を進めて、半田付けの怪しい部分を付け直します。

続いて、内部のクリーニングに移ります。

元々ホコリ等は殆どありませんでした。

次に、VR類へ接点クリーナーを吹きかけて、

ワイヤー類を点検し、

電源の投入を確認し、

キャビネットを組み戻し、各操作を点検し、

流しテストで音出し確認し作業終了です。

故障内容は、フォノ入力やチューナー入力、AUX入力の不具合とのことです。
又、部品取り機もお預かりしております。
早速、電源の投入を確認し各操作の点検を進めてみますと、フォノ入力で激しいノイズが生じます。
又、チューナーとAUXの入力も不安定です。
キャビネットを分解し、
各部の点検を進めて、インプットセレクター回路の故障と判明いたしました。
基板の細部の点検で、I.Cの不具合が見つかりまして、
部品取り機から、赤印の交換用を抜き取りこちらを移植いたします。
そして、周辺の劣化したコンデンサーを取り替えて、
各基板の点検を進めて、半田付けの怪しい部分を付け直します。
続いて、内部のクリーニングに移ります。
元々ホコリ等は殆どありませんでした。
次に、VR類へ接点クリーナーを吹きかけて、
ワイヤー類を点検し、
電源の投入を確認し、
キャビネットを組み戻し、各操作を点検し、
流しテストで音出し確認し作業終了です。
2025年05月01日
SL-1200MK2 修理 栃木県より アームベースアーシング修正修理、メンテナンス、
今回のご依頼は、SL-1200MK2 栃木県からです。


故障内容は、トーンアームに触れるとブーン音が生じるとのことです。

早速、電源の投入を確認し、各操作の点検を進めていきましょう。

制御系や音声出力は順調ですが、

トーンアームに触れるとブーン音が生じます。

各部の点検を進めてみますと、アームへアースワイヤーを繋ぐとノイズが解除されます。

ターンテーブルを抜き取り、

制御基板のカバーを取り外し、

内部のクリーニングを進めます。

元々ホコリ等は殆どありませんでした。

出力側のアースワイヤーと

アームのパイプ部分で導通が有りません。
アース浮の故障です。


底蓋を取り外し、

フォノケー基板類の点検に移ります。

カバーを取り外し、

基板の細部を点検し、

アーシングの故障と判明いたしました。

修正用のワイヤーを準備し、

緑印の両端へ結線し、赤印のL字のスプリングの取り付け位置を確認します。

取り付け位置を誤るとanti-skatingが利きません!

フォノカバーを閉じて、ピッチVRの点検に移ります。

VR類へ接点クリーナーを吹きかけて、

本体へ組み戻し、スタイラスイルミネーターは変更なしです。

各スイッチの操作を点検し、

制御基板を開いて、


半田付けの怪しい部分をつけなおします。

次に、シャフトの作業に移ります。

SL-1200MKシリーズのシャフトベースが2種類あり、こちらはシャフトギヤが圧入されたタイプです

このギヤは無理に抜き取らず、隙間から注油していきます。

モーターコイルとシャフトを組み戻し、

特殊治具を活用し

ターンテーブルを浮かせた状態で駆動させて、

ブレーキ等の調整を進めていきます。

そして、アームの取り付け部分を点検し、

ピッチVRの操作を点検します。

ヘットシェルの接触部分を点検し、

スタイラスイルミネーターへ変更なしです。

制御系を点検し、

各操作を点検し、

流しテストで音出し確認し、作業終了です!

故障内容は、トーンアームに触れるとブーン音が生じるとのことです。
早速、電源の投入を確認し、各操作の点検を進めていきましょう。
制御系や音声出力は順調ですが、
トーンアームに触れるとブーン音が生じます。
各部の点検を進めてみますと、アームへアースワイヤーを繋ぐとノイズが解除されます。
ターンテーブルを抜き取り、
制御基板のカバーを取り外し、
内部のクリーニングを進めます。
元々ホコリ等は殆どありませんでした。
出力側のアースワイヤーと
アームのパイプ部分で導通が有りません。
アース浮の故障です。
底蓋を取り外し、
フォノケー基板類の点検に移ります。
カバーを取り外し、
基板の細部を点検し、
アーシングの故障と判明いたしました。
修正用のワイヤーを準備し、
緑印の両端へ結線し、赤印のL字のスプリングの取り付け位置を確認します。
取り付け位置を誤るとanti-skatingが利きません!
フォノカバーを閉じて、ピッチVRの点検に移ります。
VR類へ接点クリーナーを吹きかけて、
本体へ組み戻し、スタイラスイルミネーターは変更なしです。
各スイッチの操作を点検し、
制御基板を開いて、
半田付けの怪しい部分をつけなおします。
次に、シャフトの作業に移ります。
SL-1200MKシリーズのシャフトベースが2種類あり、こちらはシャフトギヤが圧入されたタイプです
このギヤは無理に抜き取らず、隙間から注油していきます。
モーターコイルとシャフトを組み戻し、
特殊治具を活用し
ターンテーブルを浮かせた状態で駆動させて、
ブレーキ等の調整を進めていきます。
そして、アームの取り付け部分を点検し、
ピッチVRの操作を点検します。
ヘットシェルの接触部分を点検し、
スタイラスイルミネーターへ変更なしです。
制御系を点検し、
各操作を点検し、
流しテストで音出し確認し、作業終了です!
2025年04月30日
ヤマハ CX-1 修理 沖縄県内より プリント基板修理、各部点検調整、他
今回のご依頼は、ヤマハ CX-1 沖縄県内からです。
故障内容は、音声出力の片Chが途切れてしまうとのことです。

電源を投入し各操作の点検を進めてみますと、Rchの出力に途切れが見つかりました。

トップカバーを開いて、


底面のカバーを取り外し、

内部のクリーニングを進めます。

元々ホコリ等は殆どありませんでした。

先ず、基板内のサブ基板の接続部分や


コネクター類の点検を進めて


続いて、オシロスコープを準備し、

基板の底面の点検を進めて、

I.Cの半田付けに微かな亀裂が見つかりました。

I.Cの半田付けを修正し、半田付けの怪しい部分を付け直します。

音出し確認しキャビネットを組み戻します。

そして、各操作を点検し、

流しテストで音出し確認し作業終了です。

故障内容は、音声出力の片Chが途切れてしまうとのことです。
電源を投入し各操作の点検を進めてみますと、Rchの出力に途切れが見つかりました。
トップカバーを開いて、
底面のカバーを取り外し、
内部のクリーニングを進めます。
元々ホコリ等は殆どありませんでした。
先ず、基板内のサブ基板の接続部分や
コネクター類の点検を進めて
続いて、オシロスコープを準備し、
基板の底面の点検を進めて、
I.Cの半田付けに微かな亀裂が見つかりました。
I.Cの半田付けを修正し、半田付けの怪しい部分を付け直します。
音出し確認しキャビネットを組み戻します。
そして、各操作を点検し、
流しテストで音出し確認し作業終了です。
2025年04月29日
DENON DP-70M 修理 沖縄県内より トランジスター、コンデンサー交換修理、他
今回のご依頼は、DENON DP-70M 沖縄県内からです。
依頼内容は、ターンテーブルの回転が不安定で修理点検とのことです。

早速、電源の投入を確認し、

ターンテーブルの回転の点検を進めてみますが、

回転数が安定しません。

ターンテーブルを抜き取り、

底面のカバーを取り外し、


内部のクリーニングを進めます。

元々ホコリ等は殆どありませんでした。

モーターとメイン基板の点検を進めて

基板を開いて、

トランジスターとコンデンサーの故障が判明いたしました。

トランジスターとコンデンサーを交換し、

半田付けの怪しい部分を付け直し、

基板の細部を点検し、組み戻します。

続いて、ピッチVR基板を取り出して、


VR類へ接点クリーナーを吹きかけて、

ワイヤールを点検し


PGヘット等を点検し

電源の投入を確認し、

制御系を点検し、

各操作を点検し、

流しテストで確認し作業終了です。

依頼内容は、ターンテーブルの回転が不安定で修理点検とのことです。
早速、電源の投入を確認し、
ターンテーブルの回転の点検を進めてみますが、
回転数が安定しません。
ターンテーブルを抜き取り、
底面のカバーを取り外し、
内部のクリーニングを進めます。
元々ホコリ等は殆どありませんでした。
モーターとメイン基板の点検を進めて
基板を開いて、
トランジスターとコンデンサーの故障が判明いたしました。
トランジスターとコンデンサーを交換し、
半田付けの怪しい部分を付け直し、
基板の細部を点検し、組み戻します。
続いて、ピッチVR基板を取り出して、
VR類へ接点クリーナーを吹きかけて、
ワイヤールを点検し
PGヘット等を点検し
電源の投入を確認し、
制御系を点検し、
各操作を点検し、
流しテストで確認し作業終了です。
2025年04月28日
TEAC A-6300 修理 山口県より メカベース分解修理、トランジスター交換修理、コンデンサー交換修理、他
今回のご依頼は、TEAC A-6300 山口県からです。


故障内容は、再生の操作で早送りになるとのことです。

早速、電源の投入を確認し、

各動作の点検を進めてみますと、再生の操作で早送りの状態になります。

各部の点検で、ピンチローラーが固着しております。

裏面のカバーを取り外し、

メカベースの点検に移ります。

赤印の隠れた部分のネジを抜き取り、

フライホイール等を取り外します。


そして、ピンチローラーアームの点検で、シャフト部分の固着が判明いたしました。

アームを抜き取り、黒印の内部のクリーニングを進め


ホルダー部分もクリーニングし、

精密用のオイルを注油し組み戻します。

続いて、フライホイールのシャフトと

ホイールをクリーニングし

シャフトへ精密用のオイルを注油します。

本体の内部をクリーニングし、

ワイヤー類を点検し、

VR類へ接点クリーナーを吹きかけて、

本体の底側のカバーを取り外し、

アンプ回路の点検を進めて

半田付けの怪しい部分を付け直します。


次に、リール台のホルダーを取り外し、

カウンターベルトの取り替えに移ります。

メカベース側のカウンタープーリーからベルトを外し、

表側のリール台の隙間から抜き取ります。

白印の交換用のベルトを準備し組み付けます。

リール台を固定し、

録音や再生の音出し確認で、ノイズが生じます。

本体の底側のアンプ基板を抜き取り、

アンプ回路の点検を進めて

トランジスターや

コンデンサーを交換いたします。


ヘッドカバーを取り外し、


ヘット周辺と

走行系をクリーニングし、

次にメカを再生の状態で

ピンチローラーをクリーニングします。

そして、録音や再生の音出し確認し

各操作を点検し、

流しテストで音出し確認し作業終了です。

故障内容は、再生の操作で早送りになるとのことです。
早速、電源の投入を確認し、
各動作の点検を進めてみますと、再生の操作で早送りの状態になります。
各部の点検で、ピンチローラーが固着しております。
裏面のカバーを取り外し、
メカベースの点検に移ります。
赤印の隠れた部分のネジを抜き取り、
フライホイール等を取り外します。
そして、ピンチローラーアームの点検で、シャフト部分の固着が判明いたしました。
アームを抜き取り、黒印の内部のクリーニングを進め
ホルダー部分もクリーニングし、
精密用のオイルを注油し組み戻します。
続いて、フライホイールのシャフトと
ホイールをクリーニングし
シャフトへ精密用のオイルを注油します。
本体の内部をクリーニングし、
ワイヤー類を点検し、
VR類へ接点クリーナーを吹きかけて、
本体の底側のカバーを取り外し、
アンプ回路の点検を進めて
半田付けの怪しい部分を付け直します。
次に、リール台のホルダーを取り外し、
カウンターベルトの取り替えに移ります。
メカベース側のカウンタープーリーからベルトを外し、
表側のリール台の隙間から抜き取ります。
白印の交換用のベルトを準備し組み付けます。
リール台を固定し、
録音や再生の音出し確認で、ノイズが生じます。
本体の底側のアンプ基板を抜き取り、
アンプ回路の点検を進めて
トランジスターや
コンデンサーを交換いたします。
ヘッドカバーを取り外し、
ヘット周辺と
走行系をクリーニングし、
次にメカを再生の状態で
ピンチローラーをクリーニングします。
そして、録音や再生の音出し確認し
各操作を点検し、
流しテストで音出し確認し作業終了です。
2025年04月25日
Thechnics SU-2450 修理 沖縄県内より I.C交換修理、コンデンサー交換修理、各部点検調整、
今回のご依頼は、Thechnics SU-2450 沖縄県内からです。
故障内容は、電源が入らないとのことです。

早速、電源の投入を試みますが、起動できません。

キャビネットを分解し、内部のクリーニングを進めます。

画像では、判りにくいですがスッキリしました。

続いて、底面のカバーを取り外し、


基板の細部の点検を進めて、

コンデンサー2個で2箇所の液漏れが見つかりました。

交換用のコンデンサーを準備し、

基板を修正し、取り付けます。

そして、半田付けの怪しい部分を付け直します。

そして、電源の投入を確認し、音出し確認で左側の出力に歪が生じております。

出力回路の点検を進めて、黄色印のI.Cの故障が疑われます。

左右のI.Cを差し替えて、確認できました。

交換用の赤印のI.Cを準備し取り付けます。

そして、ワイヤー類を点検し、

音出し確認します。

キャビネットを組み戻し、各操作を点検し、

流しテストで音出し確認し作業終了です。

故障内容は、電源が入らないとのことです。
早速、電源の投入を試みますが、起動できません。
キャビネットを分解し、内部のクリーニングを進めます。
画像では、判りにくいですがスッキリしました。
続いて、底面のカバーを取り外し、
基板の細部の点検を進めて、
コンデンサー2個で2箇所の液漏れが見つかりました。
交換用のコンデンサーを準備し、
基板を修正し、取り付けます。
そして、半田付けの怪しい部分を付け直します。
そして、電源の投入を確認し、音出し確認で左側の出力に歪が生じております。
出力回路の点検を進めて、黄色印のI.Cの故障が疑われます。
左右のI.Cを差し替えて、確認できました。
交換用の赤印のI.Cを準備し取り付けます。
そして、ワイヤー類を点検し、
音出し確認します。
キャビネットを組み戻し、各操作を点検し、
流しテストで音出し確認し作業終了です。
2025年04月24日
DIATONE DSS-S67 修理 沖縄県より トランジスター交換修理、他
今回のご依頼は、DIATONE DSS-S67 沖縄県からです。

依頼内容は、各部の点検と音声出力の復旧とのことです。

早速、各部の点検を進めてみますと、黒印の部分のトランジスターが取り外されて、同封されておりました。

又、本体の底面はベニヤ板でカバーを作られております。

カバーを取り外し、

基板の細部の点検で、8個中の出力トランジスターの内、5個がショートしております。

出力トランジスターは赤印の代用品の脚を加工し取り付けます。

放熱用のグリスを塗りつけて、

ヒートシンクへ取り付けて、

クランパーで固定します。

交換前は、下の画像です。

続いて、増幅回路等の点検で、赤印のトランジスターが抜き取られております。

左側の黄色印のトランジスターで品番を確認し、

トランジスターを準備し取り付けます。

そして、ワイヤールを点検し、

半田付けの怪しい部分を付け直し、

VR類へ接点クリーナーを吹きかけて、

内部のクリーニングを進めます。

画像では、判りにくいですがスッキリしました。

基板の細部を点検し、

ベニヤ板のカバーを取り付けます。
綺麗に作られております!

電源の投入を確認し、各操作を点検し、

流しテストで音出し確認し作業終了です。

依頼内容は、各部の点検と音声出力の復旧とのことです。
早速、各部の点検を進めてみますと、黒印の部分のトランジスターが取り外されて、同封されておりました。
又、本体の底面はベニヤ板でカバーを作られております。
カバーを取り外し、
基板の細部の点検で、8個中の出力トランジスターの内、5個がショートしております。
出力トランジスターは赤印の代用品の脚を加工し取り付けます。
放熱用のグリスを塗りつけて、
ヒートシンクへ取り付けて、
クランパーで固定します。
交換前は、下の画像です。
続いて、増幅回路等の点検で、赤印のトランジスターが抜き取られております。
左側の黄色印のトランジスターで品番を確認し、
トランジスターを準備し取り付けます。
そして、ワイヤールを点検し、
半田付けの怪しい部分を付け直し、
VR類へ接点クリーナーを吹きかけて、
内部のクリーニングを進めます。
画像では、判りにくいですがスッキリしました。
基板の細部を点検し、
ベニヤ板のカバーを取り付けます。
綺麗に作られております!
電源の投入を確認し、各操作を点検し、
流しテストで音出し確認し作業終了です。
2025年04月23日
Thechnics SL-10 修理 沖縄県より アームベース分解修理、各部点検調整、
今回のご依頼は、Thechnics SL-10 沖縄県からです。
故障内容は、レコードの再生でアームが進まないとのことです。

早速、電源の投入を確認し、

制御系の点検を進めて、

各操作の点検を進めてみますと、

リニアトラックアームの動作が出来ません。

先ず、ドアの固定用のポールを解除し

カートリッジを取り外し、

ターンテーブルの中央の45アダプターやホルダー等を分解し、

ターンテーブルの中央へ2mmのボルトを取り付けて、

ターンテーブルを抜き取ります。


そして、キャビネットと

センサー基板のカバーを取り外し、

内部のクリーニングを進めます。

画像では、判りにくいですがスッキリしました。

リニアトラックアームの動作の不具合の原因を解析し

分解作業に移ります。

赤印のアームの駆動ワイヤーのニップルを取り外し、


アームベースを取り外します。

そして、シャフトと

ホルダー部分のクリーニングを進め

精密用のグリスを塗って、

本体へ組み戻し

ニップルを組み付けて、

緩み防止のペイントを塗って、ニップルを固定します。

続いて、基板のセンサー類の点検を進めて

モーター等を取り出して、

モーターシャフトへ精密用のオイルを注油し、

外部電源を活用し、

モーターへ直接電圧を加えて、注油したオイルが馴染まさせます。

モーターを組み戻し、

プーリー類をクリーニングし

ベルトとポールを組み付けて、

そして、半田付けの怪しい部分を付け直します。

尚、カバーの取付時には、赤印のスイッチに気を付けましょう。
壊れやすいですヨ、

続いて、メイン基板の点検に移ります。

基板を開いて、

半田付けの怪しい部分を付け直します。

続いて、モーターシャフトを抜き取り、分解し

シャフトのクリーニングを進めて、

精密用のオイルを塗り付けます。

次に、MM/MCの切り替えスイッチへ接点クリーナーを吹きかけます。

基板を組み戻し、

キャビネットとターンテーブルを組み付けて、

電源の投入を確認し、

テスト盤を載せて、制御系の点検を進めて、

再生の点検を進めて、

リニアトラックアームの動作を確認し


各操作を点検し、


流しテストで音出し確認し作業終了です。

故障内容は、レコードの再生でアームが進まないとのことです。
早速、電源の投入を確認し、
制御系の点検を進めて、
各操作の点検を進めてみますと、
リニアトラックアームの動作が出来ません。
先ず、ドアの固定用のポールを解除し
カートリッジを取り外し、
ターンテーブルの中央の45アダプターやホルダー等を分解し、
ターンテーブルの中央へ2mmのボルトを取り付けて、
ターンテーブルを抜き取ります。
そして、キャビネットと
センサー基板のカバーを取り外し、
内部のクリーニングを進めます。
画像では、判りにくいですがスッキリしました。
リニアトラックアームの動作の不具合の原因を解析し
分解作業に移ります。
赤印のアームの駆動ワイヤーのニップルを取り外し、
アームベースを取り外します。
そして、シャフトと
ホルダー部分のクリーニングを進め
精密用のグリスを塗って、
本体へ組み戻し
ニップルを組み付けて、
緩み防止のペイントを塗って、ニップルを固定します。
続いて、基板のセンサー類の点検を進めて
モーター等を取り出して、
モーターシャフトへ精密用のオイルを注油し、
外部電源を活用し、
モーターへ直接電圧を加えて、注油したオイルが馴染まさせます。
モーターを組み戻し、
プーリー類をクリーニングし
ベルトとポールを組み付けて、
そして、半田付けの怪しい部分を付け直します。
尚、カバーの取付時には、赤印のスイッチに気を付けましょう。
壊れやすいですヨ、
続いて、メイン基板の点検に移ります。
基板を開いて、
半田付けの怪しい部分を付け直します。
続いて、モーターシャフトを抜き取り、分解し
シャフトのクリーニングを進めて、
精密用のオイルを塗り付けます。
次に、MM/MCの切り替えスイッチへ接点クリーナーを吹きかけます。
基板を組み戻し、
キャビネットとターンテーブルを組み付けて、
電源の投入を確認し、
テスト盤を載せて、制御系の点検を進めて、
再生の点検を進めて、
リニアトラックアームの動作を確認し
各操作を点検し、
流しテストで音出し確認し作業終了です。